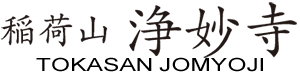開山略伝


行勇律師(1163〜1241)は相模国酒勾(小田原市)の人で初名は玄信、荘厳房と称した。
幼くして薙髪出家し、真言密教を学んだ。養和元年(1181)には鶴岡八幡宮寺の供僧となり、ついで永福寺・大慈寺の別当にも任じ、
文治4年(1188)足利義兼が当山を建立すると開山に迎えられた。
正治元年(1199)栄西が鎌倉に下向すると、その門に入って臨済禅を修め、栄西没後は寿福寺二世に任じている。
頼朝や北条政子に信任されて戒を授ける一方、「所住の寺、海衆満堂」といわれるほど信望され、実朝もあつく帰依した。
仁治2年7月、東勝寺で没した。
什宝
非公開
釈迦如来坐像(本尊)
南北朝時代 一軀

開山退耕行勇坐像
南北朝時代 一軀
※重要文化財
晩年の開山の姿を伝える優れた肖像彫刻(頂相(ちんぞう))。
個性的面貌をよくとらえている。

阿弥陀如来立像
鎌倉時代 一軀
上品下生印の来迎尊で、平政子の白檀の弥陀という。
鎌倉国宝館寄託中。

三宝荒神立像
室町時代 一軀
鎌倉では珍しい大きな尊像。
仏法僧の三宝を守り、日を防ぐ神として信仰された。

淡島大明神立像
江戸時代 一軀
当寺の塔頭直心庵に安置されていた像。
婦人病に霊験のある神。

藤原鎌足像
江戸時代 一軀
鎌倉という地名はこの像に由来すると「鎌埋稲荷明神縁起」に書いてある。

紙本淡彩地蔵菩薩像
足利尊氏自画賛
一幅
足利尊氏の地蔵信仰を物語る作品である。